避難の心得
どんなときに避難するか
- 初期消火に失敗し、燃え広がる危険性が大きいとき。
- 市町村の職員、警察官、消防職員の指示があったとき。
- ラジオや市町村などの情報や周囲の状況などから避難の必要があると判断したとき。
避難の心得10か条
1.避難する前に、もう一度火元を確かめ、ブレーカーも切る。
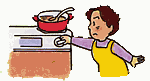
2.各自が緊急避難カードを身につける。
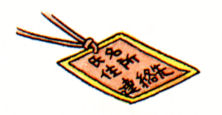
3.ヘルメットや防災ずきんで頭を保護。

4.荷物は最小限のものに。

5.外出中の家族には連絡メモを。
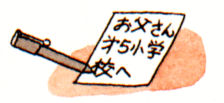
6.避難は徒歩で。車やオートバイは厳禁。

7.お年寄りや子どもの手はしっかり握って。

8.近所の人たちと集団で、まず決められた集合場所に。
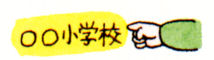
9.避難場所へ移動するとき、狭い道・塀ぎわ・川べりなどは避ける。
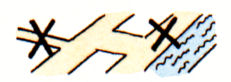
10.避難は指定された避難場所へ。
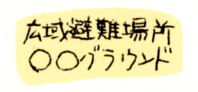
非常持出品
避難時に持ち出したいもの・・・欲ばりすぎると避難に支障が生じるので注意! 成人男性で15キログラム、女性で10キログラムを目安に

貴重品
現金、権利証書、預貯金通帳、免許証、健康保険証など
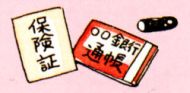
衣類
下着、上着、タオル、紙おむつなど

非常食品
乾パン、缶詰など火を通さなくても食べられるもの。ミネラルウォーター、水筒など
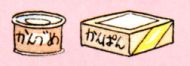
携帯ラジオ
予備電池を多めにストックしておく

応急医薬品
目薬、傷薬、胃腸薬、救急絆創膏、包帯、抗生物質など(病人やお年寄りの常備薬をわすれずに)

照明器具
懐中電灯(できれば1人1個。予備電池を忘れずに)、ろうそく(太くて短い物を。安定する)

震災後の生活を守る物資
食料品
米(缶詰やレトルトのご飯、アルファ米も便利)、缶詰やレトルトのおかず、菓子類、梅干しや調味料。お年寄りや乳幼児用の食料品も用意する。粉ミルクや離乳食、流動食、お粥など子どもやお年寄り、病人のことを忘れないように。
缶切り、栓抜きを忘れない!

水
飲料水は1日1人3リットルを目安に(煮沸してから飲む)

燃料
卓上コンロ、固形燃料

この記事に関するお問い合わせ先
総務課 地域支援・防災安全担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-5400
総務課へのお問い合わせはこちらから







